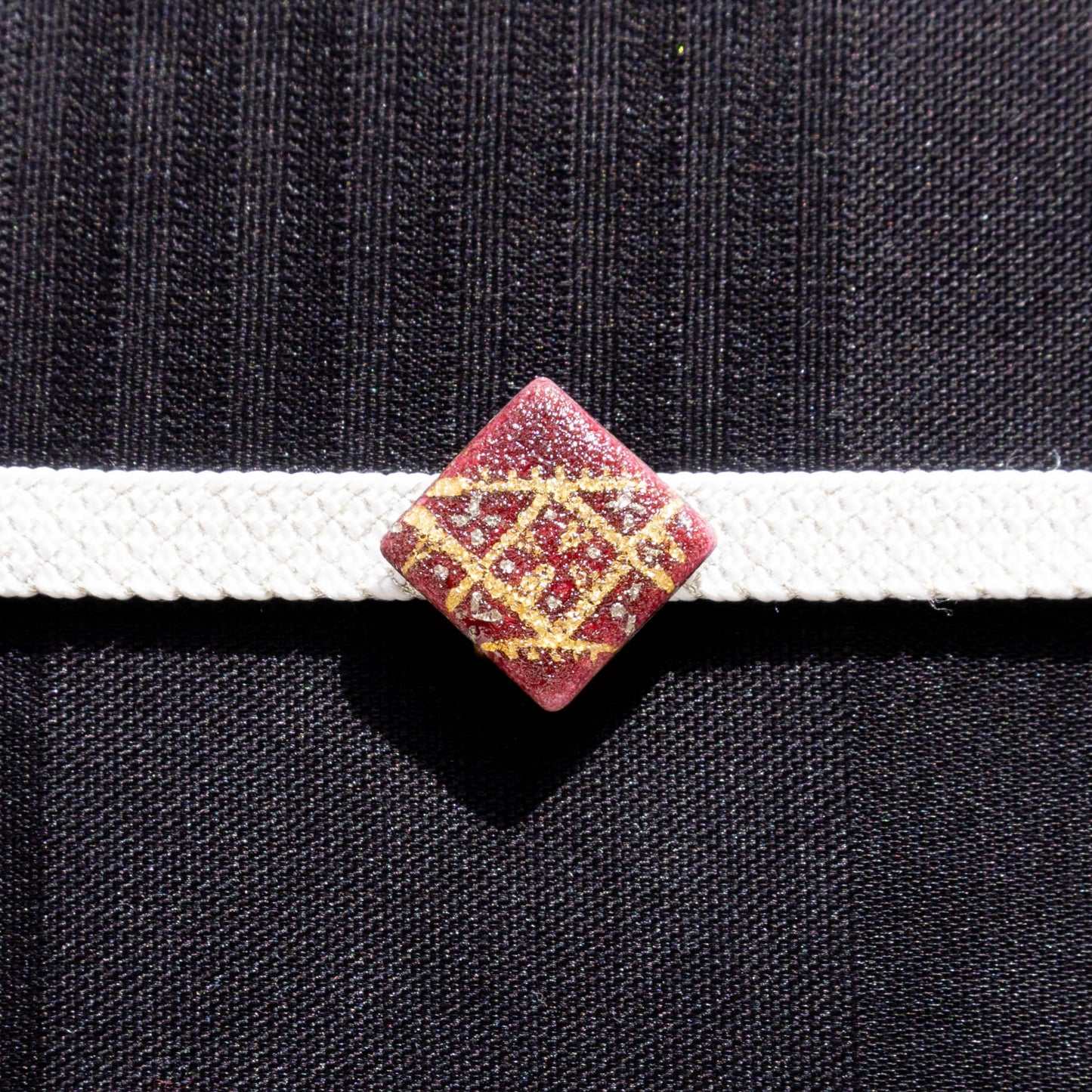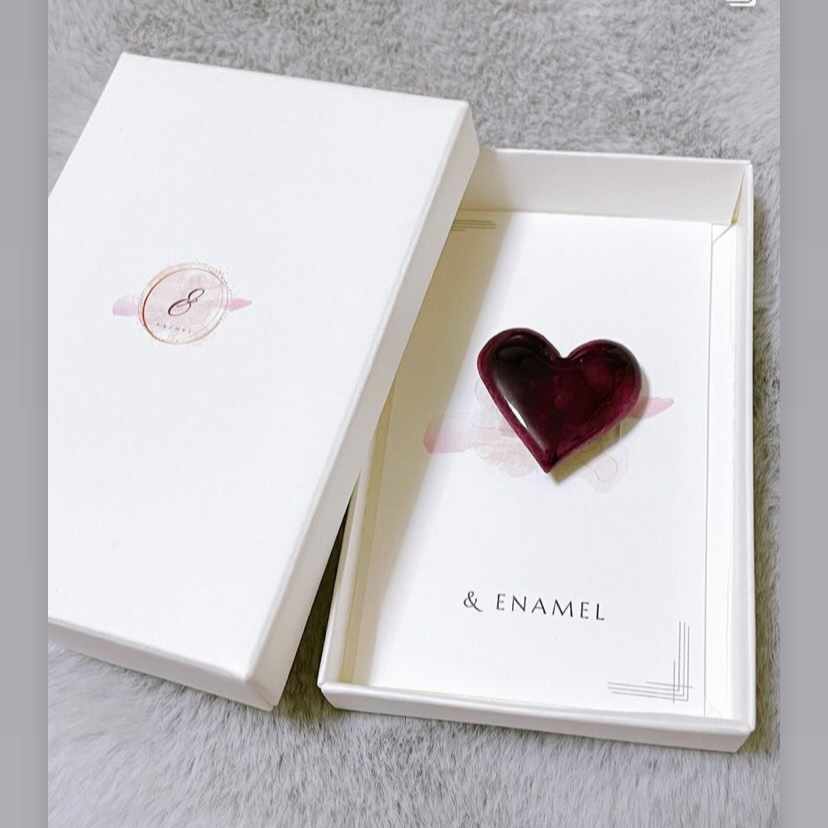こんにちは、&ENAMEL店主のアユカワです🌟
下半期の朝ドラ『ばけばけ』ご覧になっていますか?
アユカワはちょうど朝のバタバタの時間なのでうまく見れてません。。
渋沢栄一の人生を描いた大河ドラマ『晴天を衝け』のプロデューサーが指揮を執り、朝ドラだけど大河ドラマのような時代物として製作されています。
ところで作中の女性たちが着る着物について、SNS上でちょっとした議論になっていました。
それは、
「あの女性たちの半襟の出し方が、多すぎるように思うのですが・・」
SNSの投稿に集まった意見の一つに、
「NHKの朝ドラは視聴者も多く、ちょっとでも事実史実と違うとめっちゃくちゃ突っ込まれます。歴史風俗考証も非常にしっかりしているので、あれで正しいと思います」
というのがあったそうで。
製作しているのはNHK大阪局でスタッフの皆さんは大河ドラマ制作経験がないそうなんですが、もちろんこの辺りは網羅しているのですね。
ばけばけの画像を使うことはできないので、大正時代や江戸時代の人はどうだったのかなとかチラチラ確認します。

大正時代の芸者さん。
芸者なら出してるのは当たり前でしたっけ?

三代目歌川豊国、二代目歌川国久「江戸名所百人美女 堀の内祖師堂」
こちらはお百度参りをする女性。髪型は既婚女性が結う丸髷(まるまげ)で歯はお歯黒をしていますが、眉は剃ったばかりのようなので、結婚して間もない若妻のようです。
渋い色の着物の裾を広げ、青い梅模様の着物の裏地と花模様の赤い長襦袢を見せている…ということは、青いのは襦袢じゃない。こんな着方もある。

三代目歌川豊国、二代目歌川国久「江戸名所百人美女 五百羅かん」
お参りするおばあさんにお供する15、16歳の少女を描いています。少女の着物は、縦絣(たてがすり)に縦縞という江戸後期に流行した柄で、袖のあたりが透けているので夏用の絽の着物と思われる、とのこと。
赤い半衿をつけた襦袢をたっぷり見せてます、その他の小物も赤で合わせてておしゃれさん。
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
明治・大正の流行コーデは「半衿をいっぱい出す」
近藤サトさんのYouTubeが、いいタイミングでこの辺りを解説していました。
👘着物コーデの参考になるかも‼️明治・大正の流行コーデってすごい‼️令和でどうやって活かすかも楽しみ‼️
半衿についての解説は8:08あたりから。
京都で襦袢を仕立てると広衿にしてくれるって、初めて知りました。お持ちの方いらっしゃいますか?
個人的な見どころは農家の娘の半衿にプラスチックの衿芯を入れることに対する細野美也子先生の苦言です!
改めて考えると半衿に衿芯入れるのって昔はやってなくて当然。今でも何それって感じじゃないですか?普段着てる洋服にプラスチックの硬い何かが入ってるって変だもんね。
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
細野先生は『月刊アレコレ』の編集長でいらして、少し前に知って大ファンになりました。とても素敵。
あと、YouTubeの中で言われていた衿留めは、衿芯にも通じるおしゃれのためのアイテム。結構良いかもと思いました✨